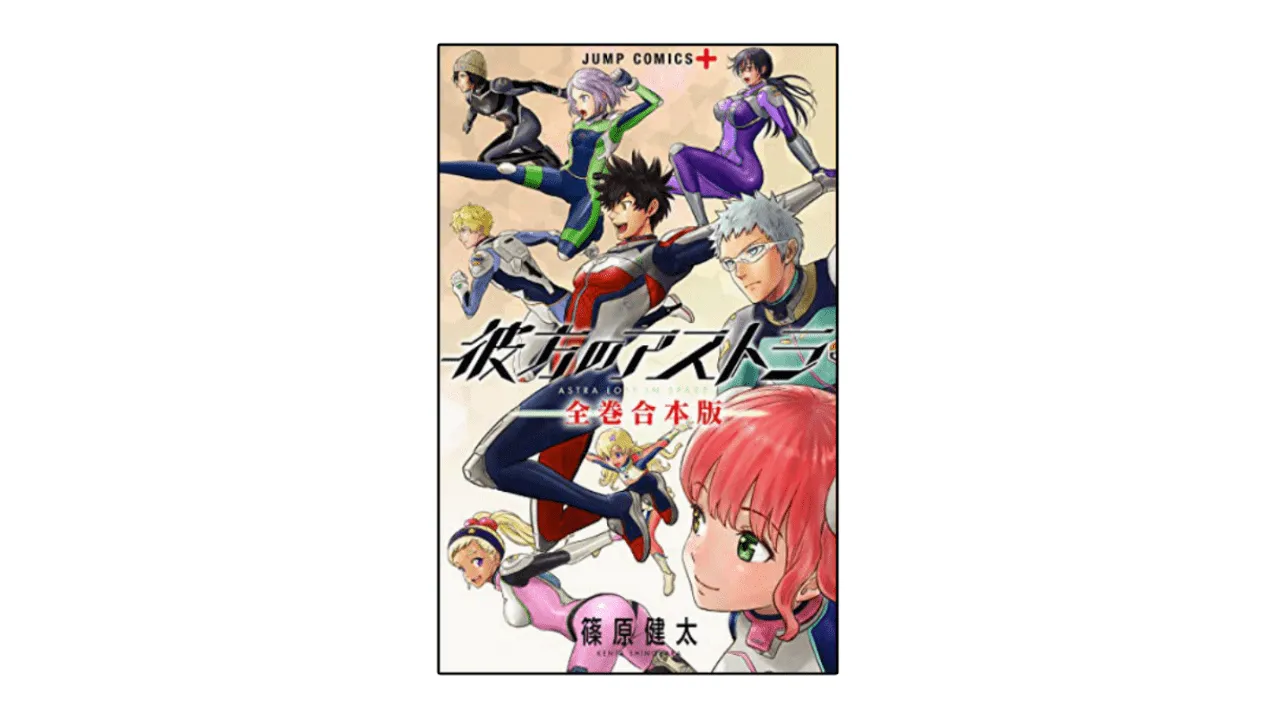※この記事にはプロモーションが含まれます。
ストーリーを創作するなら「つまらない」という評価は避けたいものです。
そこで「つまらない印象」を避ける方法を探し「脳が読みたくなるストーリーの書き方」という本を読んでみたのですが
「新人作家が書く話にありがちな、読者が読む手を止めてしまう6つのこと」
という話が面白かったのでシェアします。
作者はアメリカの元出版社員リサ・クロンさん。
漫画、小説など物語を書くクリエイターはリリース前にチェックしてみると良いかもしれません。

- もくじ
1 読者が読む手を止める6つの展開
本で述べられていた、読者が読む手を止めてしまう6つの理由がこちら。
- 主人公が誰だかわからない
- 主人公はわかるが目的がわからない
- 目的はわかるがそれを目指す理由がわからない
- ご都合主義
- 主人公の行動が目的のための行動に思えない
- 薄っぺらい
なるほど、どれもよく聞くことですが、ついついやってしまいがちかもしれません。
参考文献「脳が読みたくなるストーリーの書き方」によると、これら6つは人の脳を混乱させ、ドーパミンの分泌を止めてしまうそうです。
- 理解できなくて脳が混乱
- ドーパミン停止
- 刺激がなくなり「つまらない」と評価される
それぞれを詳しく分析してみましょう。
1-1 主人公が誰かわからない
「主人公が誰かわからない」という問題の指摘は、小説に限らず、漫画やゲームでもお馴染みです。
プロット制作の名著「SAVE THE CATの法則」等で「物語とは特定の人物の『変化』を描くもの」とされているように、物語の中で成長させたい人物を主人公と定義するといいかもしれません。
余談ですが、再アニメ化されたことで話題の漫画「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」において「真の主人公はポップだ」という評価が多いのも、物語の中でもっとも成長し、変化したのがポップだからかもしれませんな。
1-2 主人公はわかるが目的がわからない
「目的がわからない」物語では、主人公に共感したり、応援したりできなくなるとのこと。
確かに、「インディー・ジョーンズ」や「スタンド・バイ・ミー」など、シナリオが優れた映画は必ず、冒頭で主人公の目的がハッキリ定まっている印象がありますね。
マンガやゲームのシナリオでも同じことが言えるかもしれません。
- 漫画「ワンピース」:海賊王になるため、財宝ワンピースを探す
- ゲーム「ドラゴンクエスト」:世界を平和にするため、竜王を倒す
- アニメ「ラブライブ!」:廃校を阻止するため、アイドル活動で生徒を増やす
1-3 目的はわかるがそれを目指す理由がわからない
「目的と動機」がセットになっていないと、説得力に欠けるとのこと。
例えば、前述したワンピースの例に「目的」を追記すると以下のような感じでしょうか。
※次の文章の太字の箇所が「目的」
憧れの海賊シャンクスとの近いを果たし海賊王になるため、財宝ワンピースを探す
1-4 ご都合主義
「ご都合主義」が読者を萎えさせる心理は有名でしょう。
例えば、以下のようなケースがご都合主義に当たります。
- 主人公が望むものが簡単に手に入りすぎる
- 過ちを犯しても主人公だけはなぜか許される
- 作者の都合で主人公の主張がコロコロ変わる
- 作者の都合で主人公がコロコロ変わる
もちろん、主人公が望むものが手に入ることが悪いわけではありませんが、そこに至るまでには相応の試練や葛藤がないと、読者にはご都合主義と映ってしまうわけですね。
1-5 主人公の行動が目的のための行動と思えない
「物語は、主人公の目的達成に必要な場面だけ描写しろ」とのこと。さもなければ、主人公が何のために行動しているか分からなくなるそうです。あるあるですな。
たしかに、自分にとって思い入れのあるキャラクター、ストーリーであればあるほど、色んなエピソードを詰め込みたくなるものです。しかし、それでは視聴者を混乱させてしまうだけ。なので、心を鬼にしてシーンを削っていかなくてはいけません。
「より少なく、しかしより良く」の精神で、描く画面の取捨選択をしなくてはいけないわけですな。
1-6 薄っぺらい
「主人公の主張がウソくさい」「真理を言い得ていない」など、薄っぺらい印象も読者が手をとめる理由になります。
たしかに、モンスターを殺しまくってる勇者が「命は大切だ」と主張しても、白々しいことこの上ないことでしょう。
かといって、捻くれた主張をすればいいというわけでもないのでバランスがむずかしいですが、主人公の主張に説得力をもたせられる場面を、しっかり描写できるようにしておくといいかもしれません。
個人的には、初期の「カイジ」や「最強伝説黒沢」など、福本伸行先生のマンガは参考になるのではないかと思います。
読者が読む手を止める6つの展開まとめ
以上、初心者が書きがちな「読者が読む手を止める6つの展開」でした。
- 主人公が誰かわからない
- 主人公はわかるが目的がわからない
- 目的はわかるがそれを目指す理由がわからない
- ご都合主義(サクサク進みすぎたり、急に信念を曲げたり)
- 主人公の行動が目的のための行動に思えない
- 薄っぺらい(話に整合性が感じられない)
プロットを作る前後に、これら6つをチェックする習慣を付けると「つまらない」という印象を回避しやすくなるかもしれません。
2 本日の参考書:プロットづくりが学べる本

本日の参考文献は、海外の脚本書の翻訳版を数多くリリースしているフィルムアート社の「脳が読みたくなるストーリーの書き方」です。
2-1 脳が読みたくなるストーリーの書き方

こちらが本日の参考書ですが、分厚くて言葉も難しいので、読書慣れしていない方には読みにくいと思います。
てことで基本的には以下の書籍のほうがおすすめです。
2-2 SAVE THE CATの法則

読みやすいプロット本をお求めなら「SAVE THE CATの法則」のほうがいいかもしれません。
ディズニーの「アラジン」、ピクサーの「シュガーラッシュ」などで使われているSAVE THE CAT法や、ヒット映画のシナリオの型など、色んな知識が学べます。
映画の事例が多いので映画に詳しくないとピンとこないのが難点ですが、語り口調が面白いのでサクっと読めるのではないかと。
2-3 物語の法則

「プロットといえばこれ」という名著中の名著。
電子書籍版がないのが残念ですが、スターウォーズなどにも使われた「ヒーローズジャーニー理論」など、ヒット映画のシナリオ法則が学べます。