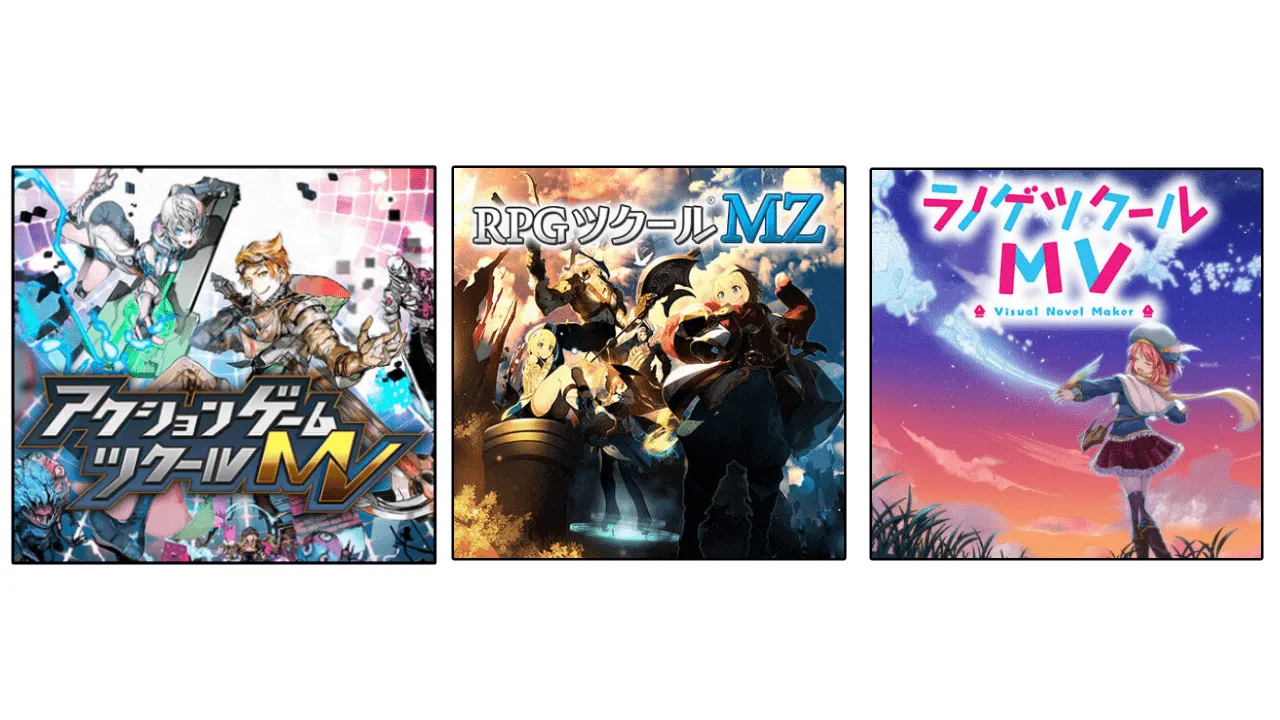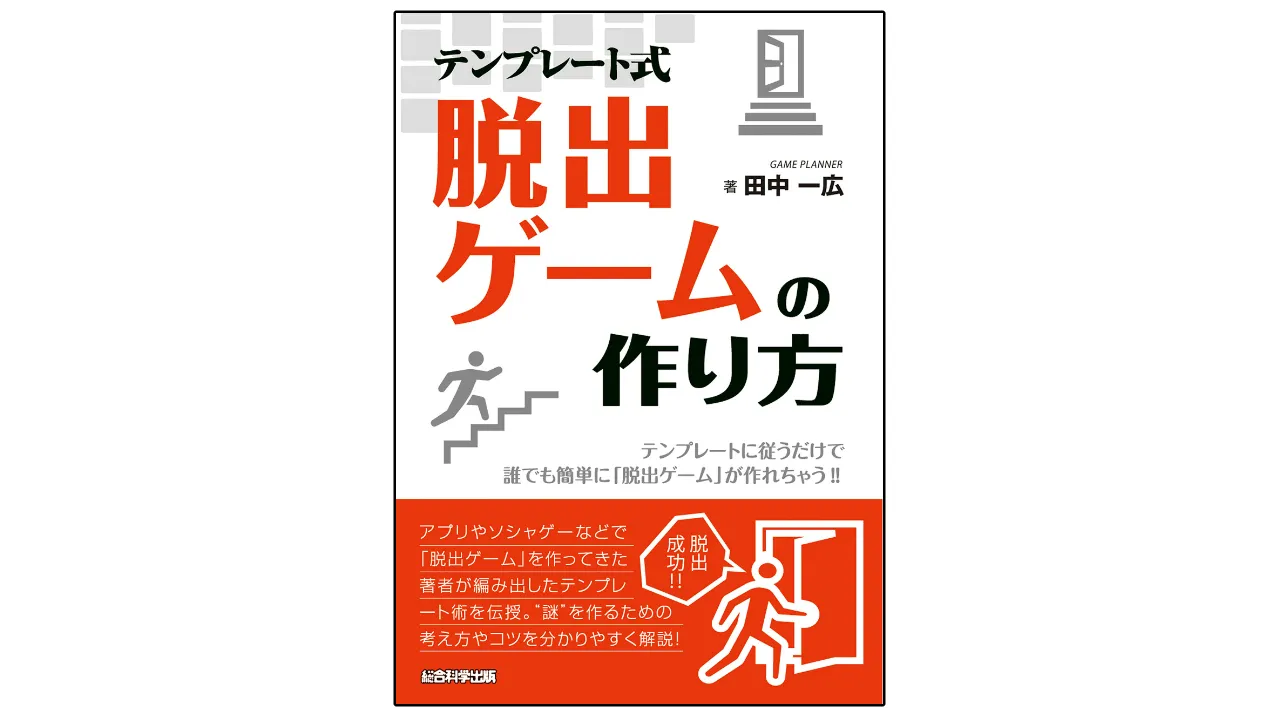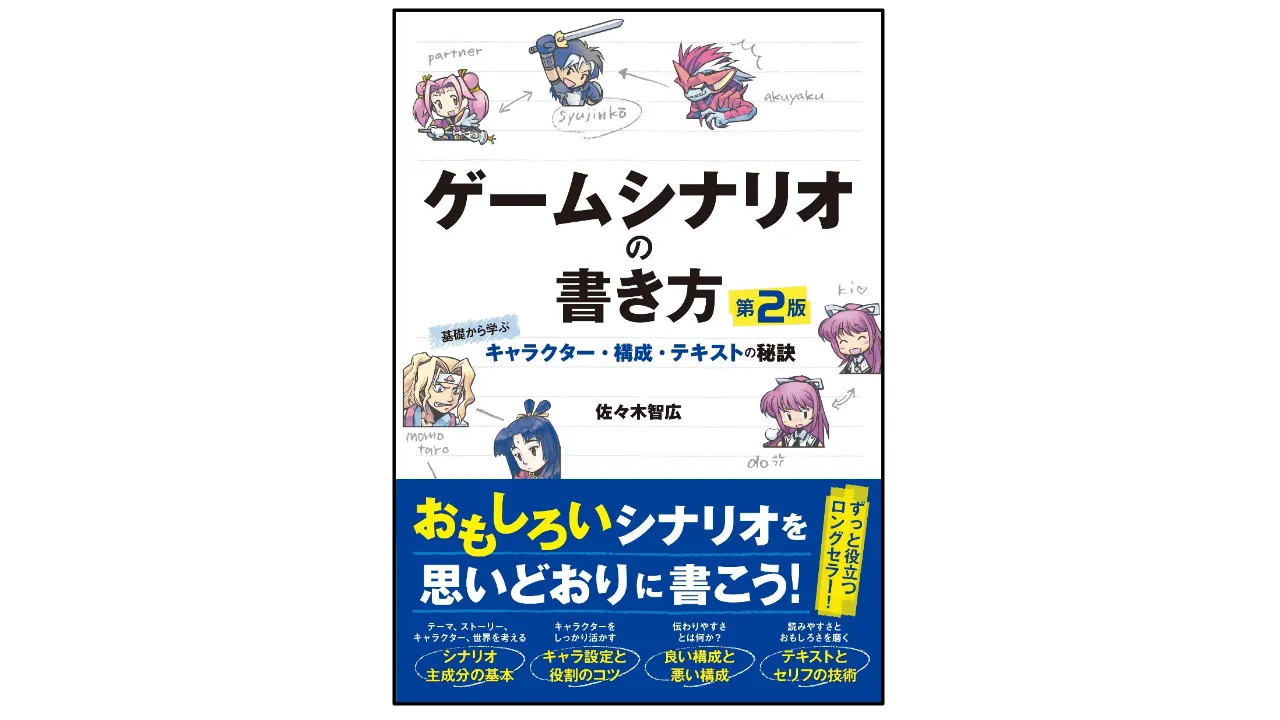※この記事にはプロモーションが含まれます。
ゲームクリエイターにとって無視できない存在といえば「ゲーム実況者」でしょう。
「青鬼」「魔女の家」など、ゲーム実況から人気に火がついたフリーゲームも多いですし、ゲーム制作する上では「どんなゲームなら実況されやすいか」をデザインすることも重要になってきます。
余談ですが、私が制作した「圧倒的ハイ&ロー」がRPGアツマールのデイリー1位を獲得できた理由も「チャンネル登録者数200万人以上の実況者さんに実況してもらえたから」でした。
今回は、ゲーム実況とゲーム制作の両方をおこなっている私の目線で「実況者がやりたくなるフリーゲームの特徴3選」をご紹介します。
- もくじ
1 「再生数が伸びそう」というフックをつくる
1つ目のポイントは、ゲーム実況者に「このゲームをやれば視聴数が増えそう」という予感を与えることです。
実況者はゲーム実況を通じてチャンネル登録者を増やしたり、収入を得たりしたいわけなので、視聴数が増えそうなゲームほど実況されやすくなります。
「再生数が伸びそう」というインパクトを与えるには、視聴者の興味を惹きそうなフックを用意することがおすすめです。
1-1 インパクトあるビジュアル
怖い、キモい、エロいなどわかりやすく感情を刺激するビジュアルはフックになります。
たとえば「青鬼」のキモカワイイ造形は思わずクリックして確認したくなるインパクトがありますし、男性がターゲットなら美少女キャラも定番でしょう。
このように、サムネイルにしやすいインパクトがある画像が毎回用意されていると、実況者は実況しやすくなります。
ゲームをつくるときは「サムネイルにしやすい場面」を30分ごとにつくってみるといいかもしれません。
1-2 インパクトあるコンセプト
タイトルやコンセプトのインパクトも、視聴者の興味を惹くポイントになるでしょう。
たとえば、以下のフリーゲームは、タイトルを読んだだけでユニークなコンセプトが伝わってきますな。


コンセプトづくりは奥が深いので、ちゃんと学びたい場合は「コンセプトのつくりかた」などを読んでみるといいかもしれません。
任天堂Wiiのユニークなコンセプトがどのようにつくられたか解説されています。
1-3 多くの視聴者が好むジャンル
「視聴者に人気のジャンルのゲーム」なこともフックになります。
もちろんチャンネルの視聴者層によって好まれるジャンルは違うものの「ホラー」「RPG」「アクション」が定番ですね。
年齢別にどんなジャンルのゲームが好まれているかは、「スマートアンサーの統計」が参考になるのではないかと思います。
2 すぐにリアクションできるよう設計する
フリーゲーム制作者がやってしまいがちなのが「テキストが長すぎて中々ゲームがはじまらない問題」です。
とくに、物語やキャラクターに思い入れがあるほどテキストが増えてしまうのはよくあることで、自分もよくやってしまいます。とほほ。
しかし、実況者は「ゲームをやりたい」のであって「物語を読みたい」わけではありません。自分でキャラを動かしてリアクションをしたり、ツッコミを入れて盛り上げたりしたいのです。
実際、私のチャンネルでもテキストが長いOPのゲームは途中離脱が多くなる傾向にあるので、OPが短くてすぐにリアクションできる作品には助かっています。
思い入れがあるほどテキストを詰めてしまうのが人情ですが、ユーザー体験(UX)を第一に考えて「もっと短く伝える方法はないか?」を思考するクセをつけておくとよさそうですな。
テキストがメインのノベルゲームの場合は、プレイヤーが選択肢を選べる回数を増やすなどして対策するといいでしょう。
3 専門用語や難しい言葉はつかわない
大衆ゲームとフリーゲームで大きく異なるのが「言葉の選び方」です。
具体的には、大衆ゲームは「漢字を減らしてひらがなを多くしている」のに対し、フリーゲームでは語彙力が試されるようなワードが多く使われる傾向にあります。
その理由として参考になるのは、心理学者ダニエル・ギルバートの研究(※1)でしょう。
- 人は理解できない言葉を話す相手を「知能が低い」と判断する
- 人は「字が読みにくいイライラ」を相手への嫌悪感としてとらえる
ゲームUXでは有名な話ですが、プレイヤーは「ゲームが上手くいかないイライラ」を、作り手への嫌悪感としてとらえます。
たとえば、ゲームが難しくてなかなか先に進めないときに「このゲーム難易度設定がクソだわ!」と作り手への怒りを感じた経験は誰でもあることでしょう。そのイライラは「テキストが読めない」場合も発動されてしまいます。
名作「風ノ旅ビト」「スーパーマリオブラザーズ」のように、文字や言葉がなくてもゲームの進め方がわかるようにデザインできれば理想ですな。
3-1 「謎解き」も誰でも解ける難易度にする
テキストと同じく気をつけなくてはいけないのが、脱出ゲームによくある「謎解き」の難易度です。
大衆ゲームの謎解きは「誰でもその場で解ける」ようデザインされているのに対し、フリーゲームは「ググらなければ解けない」デザインが多く見受けられます。
- 大衆ゲームの謎解き:大人から子供まで誰でも回答できる、例えるなら「なぞなぞ」
- フリーゲームの謎解き:高校や大学で勉強してないと回答できない、例えるなら「テスト問題」
謎解きをデザインするときは「その場にあるヒントだけで回答可能か」を考慮してみるといいでしょう。
4 ゲームUXが学べるおすすめ本

恒例の「一歩先をゆく知識が身につくおすすめ本」コーナーです。
今回は、面白いゲームの設計に欠かせない「ゲームUX」の知識が学べる本を2冊ご紹介しましょう。
4-1 「ついやってしまう」体験のつくりかた

自作ゲームをつくっている方の必読書がこちら。スーパーマリオやドラゴンクエストに散りばめられた「面白くなる仕掛け」が図解でわかりやすく解説されています。
文字が大きめで、図解説が多いので読書慣れしていない方も読みやすいのでおすすめです。
4-2 ゲーマーズブレイン

大人気ゲーム「フォートナイト」などのUXをデザインした神経心理学者による「科学的にゲームを面白くする方法」が解説されている本です。
価格が少し高めなのと、教科書のように文字ビッシリな本なので読書慣れしていない方は読みにくいかもしれませんが、ガチのゲームUXを学びたいなら読んでおいて損はありません。私は定期的に読み返すようにしています。
4-3 ゲームシナリオ入門

ゲームならではの「お約束」や「ルール」を学んでおきたい方には「ゲームシナリオ入門」がおすすめです。
「型を知らないのは型破りではなく形無しである」という言葉もあるように、人と違ったコンセプトやアイデアを生み出すために王道の知識は身につけておいて損はないと思います。